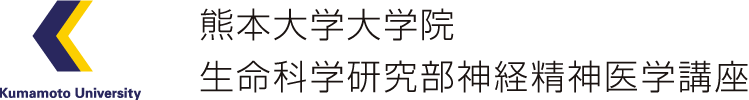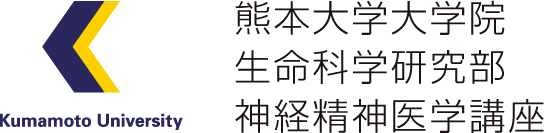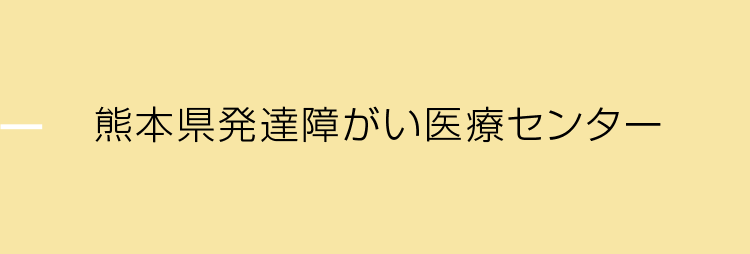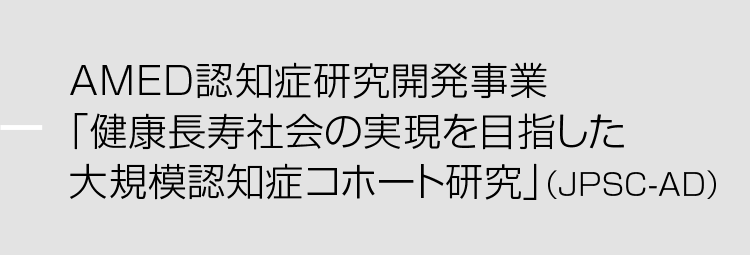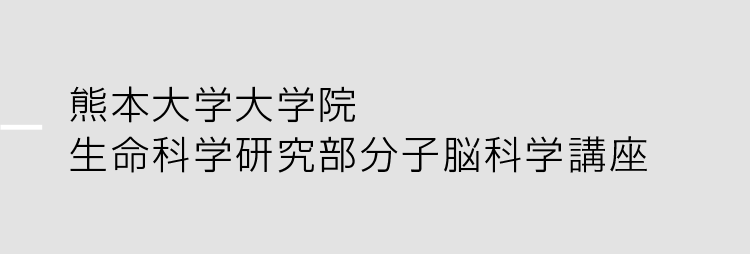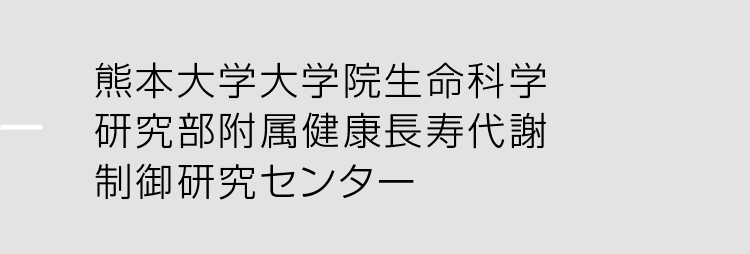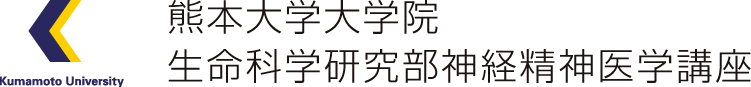専門研修
プログラム名 |
熊本大学病院連携施設 精神科専門医研修プログラム
|
基幹施設
都道府県名 |
熊本県 |
専門研修
プログラムの特徴 |
-
●背景
基幹施設となる熊本大学病院神経精神科は1904年開講の歴史ある講座で、統合失調症やアルツハイマー病の脳病理、水俣病や三池炭塵爆発のフィールドワーク、認知症医療システムなどで多くの業績を残しており、伝統的に生物学的精神医学を柱としている。現在は、気分障害、統合失調症、認知症、児童思春期精神疾患を中心としてあらゆる精神神経疾患を対象とした、バランスの良い診療・教育に注力している。
-
●教育環境
熊本大学病院の治療環境としては、西病棟2階に開放エリア38床(うち個室6床)と閉鎖エリア12床(うち4床は隔離室)からなる50床のベッドと、228㎡からなる広々とした作業療法・運動療法スペースを有する。約30名の精神科医メンターとコメディカルスタッフ(認定看護師、心理士、精神保健福祉士、作業療法士、言語聴覚士、保健師など含む)と充実した精神科チーム医療が実践できるのが特色である。県内唯一の大学病院であり、急性期・慢性期の統合失調症などの精神病性障害、気分障害、認知症などの器質性精神障害、神経症性障害、児童・思春期の精神疾患など、措置入院から任意入院まで、難治例から軽症例まで、多彩な症例を経験できる。修正型電気けいれん療法(ECT)、クロザピンも積極的に推進しており、難治・重症例の研修ができる。反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)、光トポグラフィー検査が稼働しており、最先端のうつ病治療と検査を研修できる。精神科リハビリテーションとして、認知行動療法、作業療法、リラクゼーション、ソーシャルスキルプログラム(SST)を組み合わせたリカバリープログラムを行っており、社会復帰・復職のプロセスも研修できる。また、総合病院精神科の重要な機能として、精神科リエゾンチーム、緩和ケアチームも稼働し、がんを含む身体疾患患者のメンタルケア症例も多く研修できる。さらに、熊本大学病院は熊本県から認知症と発達障害の疾患医療センターの指定をうけており、豊富な紹介症例や地域医療連携も経験できる。
-
●臨床研修内容
研修連携施設としては、熊本県内は国立病院機構熊本医療センター、国立病院機構菊池病院、熊本県立こころの医療センターと、地域の精神科医療を担っている17の民間精神科病院、県外では国立病院機構肥前精神医療センター、国立精神・神経医療研究センター病院、国立国際医療研究センター国府台病院などと、合計25施設と連携している。気分障害強化コース、認知症強化コース、児童・思春期強化コース、統合失調症強化コース、リエゾン精神医学強化コース、地域医療強化コース、子育て支援コースなど、特色ある研修メニューを用意しており、専攻医はそれらの中から選択して研修を行うことができ、研修の進捗状況によってはコース変更についても柔軟に対応することが可能である。約3年間の後期研修で、精神保健指定医、精神科専門医取得の症例をすべて経験することは十分可能であり、症例レポートの作成についても、どこでも指導が受けることができる体制を熊本大学病院で作っている。女性医師・地域枠医師のキャリア形成や医師の働き方改革にも十分配慮してバックアップを行っている。
-
●研究教育環境
専門医・指導医取得に必要な症例に関する学会発表、論文作成のサポートも推進している。また、当科ホームページにおいて、WEBによる主要精神疾患・治療法の教育セミナーを常に配信し、教育システムにも力を入れている。当研修プログラムのもう1つの特色は、臨床につながる脳科学もベッドサイドで体験できることである。臨床場面で疑問に感じたことをテーマとし、当科独自のニューロサイエンス研究室、熊本大学の分子脳科学講座と連携しながら、多角的なアプローチで「精神疾患の謎」に迫る環境にふれることで、ベッドサイドでリサーチマインドの涵養をはかることができる。
|
| プログラム内容 |
本専門研修プログラムは、日本精神神経学会による一次審査を通過したものであり、今後日本専門医機構による二次審査を踏まえて修正・変更があることを予めご承知おきください。
◎R5年度精神科領域専門医研修プログラム(xlsxファイル)
◎熊本大学医学部附属病院専門医研修プログラムページ(全診療科)
|
| 応募について |
| 応募資格 |
医師免許を有し、初期臨床研修2年修了者、あるいは、令和5年度3月に修了予定者 |
| 専攻医の募集人数 |
11人 |
| 応募資格 |
詳細は下記熊本大学病院専門研修プログラム専攻医募集のページを参照下さい。
お問い合わせは医局長(下記問い合わせ先参照)までお願いします。
◎熊本大学病院専門研修プログラム専攻医募集ページ
|
| 選考方法 |
診療科長・医局長が面接をおこないます。履歴書記載内容と面接結果に基づき厳正な審査を行い、採用の適否を判断します。医師(専攻医)は当専門研修プログラムへの採用後、研修施設群のいずれかの施設と雇用契約を結ぶこととなります。
|
|
| 施設見学について |
施設見学は随時受け付けています。こちらからお問い合わせください。
|